1.はじめに
保護猫を迎えたとき、
「名前を覚えてくれるのかな?」
「名前を呼んでも反応がない・・・」
ということがよくおこります。人間にとって名前はアイデンティティの一部ですが、猫にとっては「音の合図」でしかないからなのですが、耳が聞こえないのかしら、どこか悪いのかしら、といった要らぬ心配をしてしまいます。
特に保護猫は新しい環境に慣れるだけでも大変なので、名前を覚えさせるには工夫が必要なのです。
この記事ではにゃタゾノ主の失敗実体験を交えながら、初心者でも実践できる方法を解説します。
保護猫とのコミュニケーションを密にしたい方向けに簡単にもっと楽しく猫ライフするヒントをお届けします。
2.名前を覚えさせるための基本ステップ
2-1.名前の選び方と音の特徴
猫に覚えてもらいやすい名前は「短く」「呼びやすい音」がポイントです。
専門家によると、2〜3音程度で母音がはっきりしている名前が効果的といわれています。
例えば「ミミ」「ココ」「タマ」など。
長すぎる名前は覚えにくく、呼び方がブレやすいので避けましょう。
長い名前でも問題はないのですが、呼び方がみなバラバラだと、呼ばれた猫にとっても混乱する原因となるので、家族間でも統一ルールを設けるとよいでしょう。
保護猫の名前を決める際は、響きの良さと呼びやすさを優先するのがコツです。
「ちくわ」「つな」といった人気者になっているお名前もありますが、ねこちゃんホンポによると、「おっさん」「社長」といったおもしろい名前もあるそうです。
「佐藤おっさんちゃ~ん!」と呼ばれているかと思うとそれだけで口元がほころびます(笑)
みんなどんなヤツだろう、と振り返りますね。

佐藤おっさんちゃんの勝手なイメージ
2-2.名前を覚えさせるタイミングと頻度
また、名前を覚えさせるには「タイミング」が重要です。
- ごはんをあげるとき
- 遊びを始めるとき、
- 褒めるとき
など、保護猫にとっていいことあるぞ!と思えるポジティブな瞬間に名前を呼びましょう。頻度は1日数回で十分。しつこく呼び続けると逆効果になるので注意が必要です。猫に名前を覚えさせるためには「短時間で繰り返す」が鉄則です。
2-3.名前とポジティブな体験の関連付け
名前を呼んだら良いことが起こる、という関連付けが大切です。名前を呼んでからおやつをあげる、遊びを始めるなど、猫にとって嬉しい体験と結びつけましょう。専門家も「正の強化が最も効果的」と指摘しています。
また、お迎えしてからの数日から1週間は環境になれることでもストレスになっていることが多いので、反応がなくてもそのうちいずれ、と思い、呼ぶことをやめずに、こちらの習慣を続けていくのがよいでしょう。猫は人間の聞こえない音も拾っているので、呼ぶときの感情面も話していなくても伝わっています。
保護猫が名前を覚える過程は、まさに「音=幸せ」の学習なのです。
3.呼び方の工夫で反応が変わる
3-1.声のトーンと抑揚の使い方
猫は人間の声のトーンに敏感です。
- 高めで柔らかい声は安心感を与える
- 低く強い声は警戒心を呼ぶ
このような特徴があります。猫を呼ぶときのコツは「優しく、少し高め」。まるで子どもに話しかけるような声がベストです。まさしく猫は2‐3歳児くらいの脳の発達があるそうなので、2-3歳児に話しかけていくようなイメージがよいようです。また、抑揚をつけることで、猫は「これは特別な音だ」と認識しやすくなります。
3-2.呼び方のバリエーションとニックネーム
名前を覚えさせる際は、呼び方を統一することが基本ですが、慣れてきたらニックネームも活用できます。「ミミ」なら「ミーちゃん」「ミー」など。
ただし、最初は一貫性を保つことが重要です。猫に名前を覚えさせる段階では混乱を避け、慣れてからバリエーションを増やすとよいでしょう。
3-3.名前を呼ぶときの環境と状況
名前を呼ぶ環境も大切です。静かな場所で呼ぶと猫は集中しやすく、騒がしい場所では反応が鈍くなります。音がたくさん聞こえているので聞き取りにくい状態なのかもしれません。
さらに、猫がリラックスしているときに呼ぶと覚えやすいようです。猫を呼ぶときの呼び方は「環境+タイミング」で効果が倍増します。
4.名前を覚えにくい猫への対応
4-1.警戒心が強い保護猫の場合
保護猫は過去の経験から警戒心が強い場合があります。こうした猫には、無理に近づかず距離を保ちながら名前を呼ぶことが大切です。反応を得ようとするよりも、独り言のように、
- ○○ちゃん、おはよう
- ○○ちゃん、今日はいいお天気みたいだね~
のような声かけで、自分のことをきにかけてくれているのだ、自分に話かけているのだ、ということがわかるようになり、信頼関係が深まると反応してくるようです。
おやつや遊びを通じて「名前=安心」と関連付けることで、徐々に反応をまつ、といったところです。
4-2.多頭飼いで混乱しやすい場合
多頭飼いの場合、自分を呼んでいるのか、他の猫を呼んでいるのかわかりにくいため、猫にとっても名前が混乱しやすいものです。
呼ぶときは必ず目を合わせ、個別に名前を呼ぶとよいでしょう。猫に名前を覚えさせる際は「誰の名前か」を明確にすることが重要です。

ん?呼んだ?
複数の猫が同じタイミングで反応すると混乱するので、個別に呼んで褒める習慣をつけましょう。
4-3.年齢や体調による影響
シニア猫や体調が悪い猫は、名前を覚えるのに時間がかかることがあります。
また、先にもお伝えした通り環境の変化に対応できていないうちも含め、シニア猫や体調が悪い猫の場合は焦らず、短時間で繰り返し、優しく呼び続けることが大切です。
専門家による著述を調べても「年齢や体調に合わせたペースが必要」と強調されていることがおおいようです。
保護猫に名前を覚えさせるには、猫の状態を尊重する姿勢が不可欠ですね。
5.猫の歴史とにゃタゾノに名前を覚えさせた工夫
私が初めて保護猫を迎えると決めたときにまず家族で議題にあがったのが名前についてでした。
「からあげ」だの、「たま」だのいろいろ出てきましたが、写真を見てきめました。呼んでいるうちに長い名前は呼ぶ側も面倒になり、結局2音になっています。
猫は約9500年も前の古代エジプトで、穀物をネズミから守るために、リビアヤマネコが飼い猫として家畜化されたようで、日本に入ってきたのは弥生時代とか、平安時代とか諸説ありますが、江戸時代では「みけ」「とら」「たま」が主流だったそうです。
サザエさんちの猫も”たま”ですね。
これを見ても、2音が人間にとっても猫にとってもクリーンヒットしている名前なのではないでしょうか。
お迎え後にゃタゾノの環境になれるのと、主が猫がいることになれるための時間が必要でしたが、やっぱり2音が呼びやすく、子猫から成猫になってからは、独り言のように「ねぇ、にゃたちゃん、○○で△△だったんだけどそう思う?」と普段はなさないような気持ちをつぶやいてみたりすることで、なんとなく通じる感覚がでてきました。
そして、そんなことを数重ねていって「しつこさは逆効果」「ポジティブな関連付けが成功の鍵」ということを学びました。
6.まとめ
保護猫を飼い始めの初心者さんにとって名前を覚えさせるには、短く呼びやすい名前を選び、ポジティブな体験と関連付けることが重要です。
猫に名前を覚えさせる過程では、声のトーンや環境にも配慮し、猫の呼び方を工夫することで反応が良くなります。
警戒心が強い猫や多頭飼いの場合は、それぞれの猫に個別に対峙するという対応が必要です。
焦らず、猫のペースに合わせて進めることが信頼関係が築かれていきます。
名前を覚えることは単なる合図ではなく、猫との絆を深める第一歩。あなたの呼び方ひとつで、保護猫との暮らしはもっと楽しく、もっと幸せになっていきます。
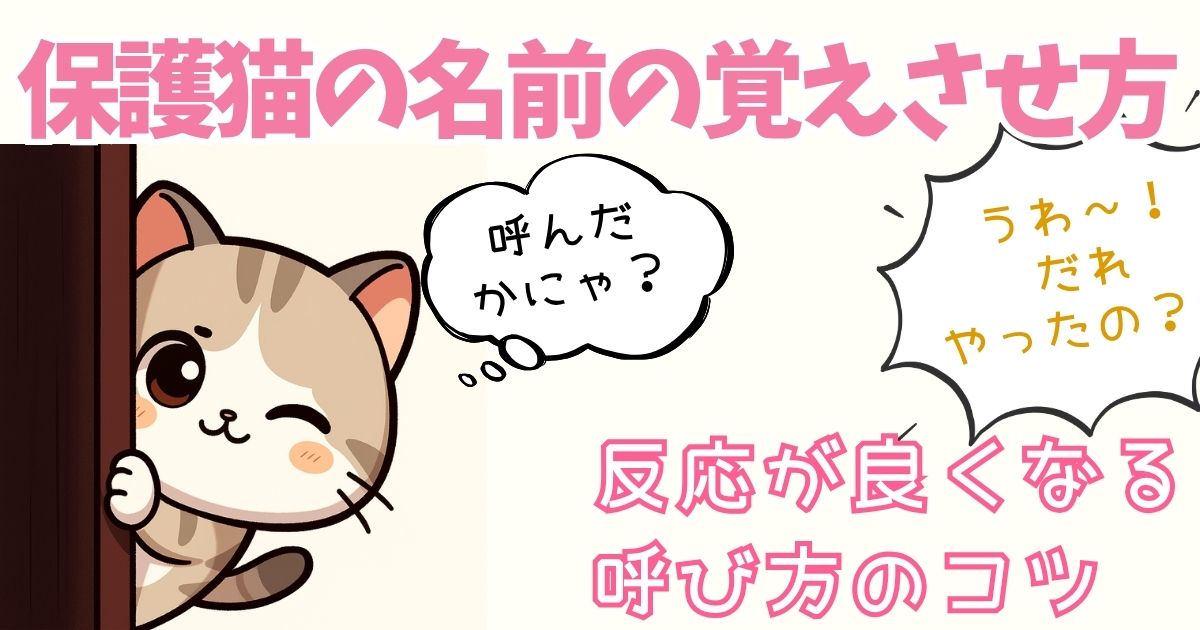


コメント