1.はじめに
保護猫をお迎えして一番ショックだったのは、にゃタゾノの耳ダニでした。外での暮らしの保護猫はノミやマダニなどのトラブルを抱えていることが多いんですね。
保護猫を初めて迎える方や猫初心者は特にビックリされることかと思います。保護猫との暮らしは幸せそのものですが、その“もふもふ”な寝顔の裏側にひっそり潜むノミやマダニたち——放置すると、健康被害はもちろん、家族にも跳び火しかねない問題児たちです。
初心者ほど対策が命綱となるため、対策の選び方からおすすめ駆除薬の特徴、動物病院と連携したベストプラクティスまで、実体験や最新情報を総まとめしました!
猫を飼い始めた方も、すでにベテランになりかけている方も、ノミ・マダニ撃退のコツがわかるようにお届けしてまいります。

はじめての病院でぐったりのにゃタゾノ
2.ノミ・マダニの基礎知識とリスク
2-1. ノミの特徴と猫への影響
ノミは猫や犬、人間にも寄生し、猫の場合は主に「ネコノミ」がつきます。見た目は小さく、体長1〜3mm程度ですが、その跳躍力は驚異的で、自分の体長の100倍も飛び跳ねます。ノミは13℃以上で活動・繁殖し始め、室内の環境でも繁殖サイクルが維持されるため、油断しているとあっという間に大繁殖。特に、1匹見つけたら周囲には数十〜数百の卵や幼虫が潜んでいると言われます。
猫がノミに寄生されると、激しいかゆみやかきむしり、脱毛、皮膚炎(ノミアレルギー性皮膚炎)が発症します。アレルギー体質の猫が1匹のノミに咬まれただけでも背中や腹、尾の付け根などにブツブツや広域脱毛、赤み、滲出性のかさぶたが現れることも。
また、子猫や体力が低下した猫では、大量に吸血されることで深刻な貧血が引き起こされ、最悪の場合は命に関わります。
ノミの体内には瓜実条虫(サナダムシ)の幼虫が住んでいることが多く、猫のグルーミング中にノミが体内へ入り込み、消化管寄生虫症まで引き起こすこともあるのです。
しかも、人間が寝ている布団で一緒に増殖し、飼い主にも強烈なかゆみと腫れをもたらすため無視できません。
ここで一番お伝えしたいのは、“見えているノミ”は氷山の一角——成虫は全体の5%もいない計算。卵や幼虫・さなぎ等“目に見えない世代”が室内のカーペットやベッドなど至るところに身を潜めているのです。
つまり、通年予防が必須。ノミ皮膚炎や瓜実条虫(うりざねじょうちゅう)の腸症状※が現れ始めたら早めに駆除と環境清掃を徹底しましょう。
※下痢、腹痛、食欲不振、体重減少などの消化器症状。虫体の一部(片節)が肛門を刺激するため、お尻を気にして舐める、床にこすりつけるといった行動もよくみられます
2-2. マダニの危険性と感染症
マダニはノミよりも大型で、吸血前でも数mm(吸血して膨らむと1cm超)になるクモ系の寄生虫です。宿主の皮膚にしっかりと口器を食い込ませ、数日間吸血を続けます。マダニのいる草むらや公園、ベランダの植栽、河川敷や裏庭などを経由して、猫に付きます。ここで怖いのが、マダニが“ただの血泥棒”ではなく、命に関わる感染症(SFTS:重症熱性血小板減少症候群)やリケッチア症、日本紅斑熱などを媒介する“厄介なバイオテロリスト”である点です。
マダニが媒介するSFTSウイルスは、吸血されることで猫自身が発症すると元気消失や発熱・黄疸などの重篤な症状を呈し、高い致死率を持ちます。特に保護猫で外生活経験がある個体、または脱走経験のある猫は要注意です。人への“キス”も危険で、マダニに吸血された際にウイルスが人にも伝播、国内死例も報告されています。一方、ダニの死骸やフンが空気中に舞うことで、猫も人も「アレルギー性鼻炎」「喘息」など、生活に支障大なアレルギー症状を発生させることも。油断ならぬ、まさに“どこでも警報”な害虫なのです。
2-3. 保護猫が特に注意すべき理由
保護猫の多くは元野良や多頭飼育崩壊出身であり、“ノミ・マダニのワンダーランド”に住んできた経験を持っています。水や餌の管理が徹底できていない、外気や動植物と頻繁に接触する、消毒が難しい環境などが背景にあります。結果、捕獲・保護された瞬間にもすでに大量のノミ・マダニに寄生されたままなことが多く、家庭に迎え入れた後は「室内大繁殖」の危険性が一気に高まります。
さらに、室内飼育でも“ノミは油断禁物”。飼い主や家族の衣類、靴、宅配のダンボール、来客者の持ち物などから巧みに侵入するため、たとえ“シティ在住・猫専用部屋”でも「うちは大丈夫♪」とは一言も言えません!また、多頭飼いの家庭では、1匹に寄生したノミがゆうゆうと他の猫や犬、さらには人間にも伝播します。したがって、“保護した直後は必ず隔離→動物病院で駆除薬&寄生虫チェック”がスタートダッシュの鉄則です。
保護猫と暮らし始めたその日から、ノミ・マダニは「わが家の敵」に早変わり。知らぬふりは通用しません。一致団結して、早期発見&即対処の姿勢が家庭の平和に直結します。

かゆみと病院疲れで爆睡
3.おすすめの猫用駆除薬と予防法
3-1. 市販の駆除薬の種類と特徴
猫用ノミ・マダニ対策の市販薬&処方薬は大きく分けて「スポットオンタイプ(滴下式)」「経口薬(チュアブル、錠剤)」「スプレータイプ」「首輪タイプ」の4種類です。どれを選ぶのかは猫の性格、健康状態、生活環境によって決めましょう。以下に代表的なタイプの特徴をまとめます。
| タイプ | 主な特徴 | 投与頻度 | 代表的な製品 |
|---|---|---|---|
| スポットオン | 首に垂らす液体、滴下するだけで高い持続性。即効性&予防効果も強い。初心者でも簡単。 | 月1回 | フロントラインプラス、ベッツワン、キャットプロテクトプラス |
| 経口薬(チュアブル) | おやつ感覚の食べる錠剤。速効性あり。滴下薬が苦手な猫に有効。 | 月1回 | ネクスガード キャットコンボ、クレデリオ錠 |
| スプレータイプ | 全身に吹きつける即効型。局所的に使え、寝具や環境にも使えるが、持続力は短い。 | 必要時 | フロントラインスプレー、ペティオ、VET’S BEST |
| 首輪タイプ | 装着するだけで長期間予防。2〜3か月交換。外出猫やシャンプー嫌いにも。 | 2-3か月 | アース・ペット、キャティーマン、セレスト |
スポットオンタイプは初心者に特におすすめです。「フロントラインプラス」は動物病院でも圧倒的な信頼度で、1本で24時間以内にノミ・48時間以内にマダニを駆除、さらに卵や幼虫の発育もシャットアウト。ジェネリック薬も多数あり、効果を保ちつつコストカットできます。
経口タイプ(ネクスガード キャットコンボ、クレデリオ)は、外用剤を嫌がる猫や皮膚疾患持ちの猫に有効です。なお、2025年現在、日本国内での認可状況に注意が必要で、輸入や動物病院限定のケースもみられます。スプレータイプや首輪タイプは、猫の性格や生活スタイルに合わせて選択を。ただし犬用成分(特にペルメトリン)は猫に絶対NGなので、購入時は細心の注意を払いましょう。
3-2. 予防法の選び方と使い方
予防法選びでは、猫のライフスタイル(完全室内か、半外出かなど)、家族構成、多頭飼いか、皮膚疾患や年齢・持病の有無を重視します。
基本は月1回の投与が目安。スポットオンタイプは肩甲骨間(首の後ろ寄り)に直接滴下すると開かいかいしたときにも手が届かない位置なので、薬をなめなめすることがなく安心です。被毛をしっかり分け、“皮膚そのもの”に塗るのがコツです。
経口薬は、おやつ代わりに食事後に与えると吸収効率が高まります。
スプレータイプは必要時に迅速な対応型で、寝具や周囲の環境にも併用可能。ただしスプレー音が苦手な猫には要注意。その場合は無香料やマイルド処方、静音設計の製品を選びましょう。
猫ごとの注意点も重要です。生後8週齢未満や2kg未満の子猫、腎臓・心臓疾患やシニア・妊娠授乳中の猫には使える薬が限定されるため必ず獣医師に相談しましょう。特にスポットオンを使う際は、皮膚トラブルの有無、シャンプーとの併用タイミングなどにも配慮を。多頭飼い家庭では、全頭同時に投薬しないと予防効果半減となります。
3-3. 初心者が注意すべきポイント
1. 動物病院でのチェックは必須!
いきなり市販薬を使うのはNG。保護したばかりの猫は複数の寄生虫感染が想定されるため、ノミ・マダニだけでなく回虫や条虫の駆除計画も同時進行が安全。特に、目視でノミを確認した時は、駆虫薬投与後も数日間は死骸やフンが出やすいので皮膚炎や誤食に注意しましょう。
2. 用量・用法は体重ごとに厳守。無理な使い回しや大型ペット向けの分割流用は厳禁。
3. ノミ駆除後も環境清掃を徹底。成虫の駆除後も卵や幼虫は2〜4週間生き残るため、根絶のためには掃除・洗濯・熱処理(60℃以上)・スチームアイロンなどを組み合わせましょう。
4. 犬用・人用成分は絶対厳禁。「ペルメトリン」「ティーツリーオイル」等は猫に猛毒です。
駆除薬の副作用・異常反応(皮膚の赤み、嘔吐、食欲不振等)が疑われた場合は、すぐに投与を中止して病院で相談しましょう。「効いてるか不安→追加投与!」は誤り。必ず投薬間隔や量を守り、“心配ならまず獣医師確認”が鉄則のようです。
4.保護猫との暮らしで気をつけたいこと
4-1. 定期的なチェックとケア
猫本体と環境、両方のケアルーチンを徹底することが効果的な対策の要です。まず被毛のチェックですが、猫の毛を分けて「跳ねる小さな虫」や「黒い粒(ノミの糞)」を探します。ノミ取りコーム(櫛)は初心者の強い味方。白いティッシュの上でコームをかけると、黒い粒が赤茶色に滲む(=ノミの糞)かチェックできます。同時に尻尾の付け根、首、腹、内股などを念入りに観察。特に普段グルーミングが苦手な高齢猫や、毛の長い猫は入念なブラッシングとチェックを推奨。
掃除においては、カーペットや布団、猫ベッド・マット、クッションの奥や家具の隙間に潜む卵や幼虫を吸い取るため、掃除機+熱処理(60℃洗濯・スチーム処理)が効果的。部屋全体を週2回以上、特に夏・梅雨どきは重点的に行いましょう。複数ペット飼育世帯では、同居動物すべての同時対策が不可欠です。
また、猫の寝具やブランケットは最低週1回、熱湯洗いや天日干しをし、環境の湿度は50%以下を目安にエアコン除湿や換気も定期的に行いましょう。グルーミングやスキンシップ、全身チェックも大切な健康観察タイム。なお、ノミ対策のブラッシングはスキンシップ(=信頼関係構築)にもなります。猫初心者にとって一番の「ご褒美タイム」と捉えると続きやすいでしょう。
4-2. 室内飼いでも油断禁物
すべての猫に共通する落とし穴、それが“室内なら安心説”のウソです。
完全室内飼いはいまだに感染リスクがゼロではありません。人の衣服・靴、宅急便やダンボール、網戸越しの虫の侵入、ベランダではノミ・マダニの“スタートダッシュ”がしばしば発生します。
温度と湿度に安定した室内環境はノミやマダニにとって快適そのもの。1年中(特に暖房使用環境下)繁殖するため、春~初夏だけの対策は不十分です。
猫の健康を守るには、定期的な駆除薬投与と環境ケアの両立を一年を通じて徹底しましょう。特に多頭飼いの場合、“感染拡大→全頭投与”がルールと考えるとよさそうです。
4-3. 動物病院との連携
保護猫や初心者こそ、動物病院との二人三脚が上達の近道です。ノミ・マダニ対策は自己流だと思わぬトラブルや事故になりがち。獣医師は年齢・体重・健康状態・生活環境に合わせて最良の薬やケア方法を選んでくれるだけでなく、正しい投薬デモや副作用時の緊急対応もレクチャーしてくれます。特に、目に見えるノミやマダニを発見した場合、あるいは皮膚炎や下痢等の合併症がみられる場合は「<即受診・対処>が最善策」。
保護直後の検便(→条虫、回虫などの内部寄生虫チェック)、ノミ発見時の追加検査、そしてワクチン接種や避妊去勢手術などトータルでサポートが受けられます。自己判断できない・不安なときは迷わず連絡しましょう。動物病院でしか扱えない強力な駆除薬やオールインワン処方薬(ノミ・マダニ+フィラリア+消化管虫同時予防)も多いので、初心者にはむしろ「費用対効果もベスト」なことが多いのです。
5.体験談:猫初心者が保護猫のノミ・マダニ対策で学んだこと
にゃタゾノは野良でもまだ子猫で比較的早い段階での保護だったので、運よく耳ダニだけですみましたが、それでもとてもかゆそうでした。家族も鼻炎もちやアレルギーがあるものもあり、急いで猫用シャンプーを買い求め、嫌がるにゃタゾノに引っかかれながらお風呂に入れました。
病院で診断されて返ってきてからは、家中の床をふいたりはいたり掃除もしたし、カーテンを洗ったりアルコール消毒したりしましたが、なにより、にゃタゾノ自身がとてもかゆそうで、耳ダニだと耳の中でみえにくいため、家ではなにもしてあげられることがなかったのです。
フロントラインは購入も気軽にできるものではありましたが、やはり初心者さんは獣医さんと相談される方がよいと考えています。
検査しもう大丈夫判定をいただいた後でも、耳をかきかきしていると「大丈夫か?!」と心配になりますが、猫が毛をよくむしる・首付近を気にするなどの行動パターンが残ったときは「ノミアレルギー皮膚炎」「死骸アレルギー」を疑い、病院で抗炎症薬を処方してもらうとよいようです。
シャンプーやスプレーだけに頼ると根絶はまず不可能ともいわれます。
また、首輪タイプについては、成分・サイズ選びと安全装着のコツがあるようなので獣医さんにおしえてもらうとよいでしょう。
脱走防止もあり、今では室内猫ですが、主のように猫ビギナーは猫のためにもその方がよいな、と感じています。本当は犬のように散歩してみたいですけどね。
6.まとめ
保護猫と暮らすなら「ノミ・マダニ対策」は、避けてはとおれません。家族にとっても家族の一員の猫にとっても健康は大事です。
小さくて見えない驚異ではありますが、やつらは数や攻撃力で勝負してきます。
ノミ・マダニなどの問題は、単なるかゆみの問題だけでなく、猫も人間もQOL低下となります。部屋全体の環境悪化など多方面にも影響をもたらします。
薬の信頼性や安全な使い方や適した種類のガイダンスをおさえて、獣医さんと相談しながら、例えば、通年で(月1回)の予防と環境清掃ルーティンを決めておくとよさそうです。
そして異常時には、迷わず「即病院」という基準値を家族と相談しておくとよいですね。


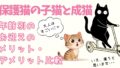
コメント