猫は夜行性ではない?本当は“薄明薄暮性”という生態
多くの人が猫は夜行性だと思っていますが、正確には「薄明薄暮性(はくめいはくぼせい)」です。
これは、夜ではなく“朝と夕方の薄暗い時間帯”に最も活発になる生態のこと。
リビアヤマネコから続く生態の名残
猫の祖先であるリビアヤマネコは、砂漠で昼間は暑すぎるため、気温が下がる朝・夕に狩りをしていました。
そのため現代の猫も、明け方や夕方になると本能的に“狩りモード”がオンになるのです。
夜に走り回る理由は「生活環境の影響」
現代の家猫は、飼い主の生活リズムに合わせて日中寝る時間が増えます。その結果、
・日中よく寝る
・夕方に刺激を受ける
・夜に備えて体力が満タン
→ 夜の大運動会が発動
という流れが起きます。
夜に活発になる“5つの本能的な理由”
猫が夜に活発になるのは、ただの癖ではなく、明確な生態・本能の結果です。
① 狩猟本能がピークになる時間帯だから
薄明薄暮性の猫にとって、夜〜早朝は狩猟タイム。家猫でも、
「音に敏感になる → 走る → 飛びつく → 物陰を狙う」
という一連の“狩りスイッチ”が入りやすくなります。
② 日中の刺激不足(退屈)
猫は1日のうち12〜16時間を寝て過ごす動物です。しかし、
・遊び時間が少ない
・環境に変化がない
・飼い主の外出時間が長い
これらが重なると、体力とエネルギーが夜まで温存されるため、夜に爆発しやすくなります。
③ 飼い主の生活リズムの影響
人の帰宅時間(夕方〜夜)は、猫にとって「刺激が入る時間」。
帰宅 → ごはん → 遊びの期待 → 興奮
というスイッチが入り、夜間の活発さにつながります。
④ トイレ後の興奮(排泄ダッシュ)
排泄時は無防備になるため、野生では危険な瞬間でした。その名残で、猫はトイレ後に興奮状態になります。
深夜にこれが起きると、突然の全力ダッシュに見えるのです。
⑤ 夜は静かで動きやすい環境
猫は環境に敏感な動物。夜は静かで、物音も少なく、狩りに適した環境です。
そのため、“動きやすい時間”として自然に行動が活発化します。
夜の大運動会を減らす“効果的な対策”5選
夜に騒ぐ猫を完全に止めることはできませんが、本能を満たしつつ静かにさせる方法はあります。
① 夕方〜夜に10〜15分の「狩り遊び」
羽根じゃらし・紐系おもちゃで、
見つける → 追う → 捕まえる → ご褒美
の流れを作ると、猫は満足して夜の運動が減ります。
② ごはんのタイミングを工夫する
夕飯後に遊ぶと食欲が増し、満腹で眠くなるため、夜の興奮を抑える効果があります。
③ キャットタワーや動線を整えて疲れやすい環境に
高いところ・移動ライン・隠れ場所を複数用意すると、日中の活動量が増えます。
④ ストレス要因(騒音・来客・環境変化)を減らす
ストレスは猫の興奮を増幅します。環境が安定すると夜の活動も穏やかになります。
⑤ 自動おもちゃや知育玩具を活用
留守中にも動くおもちゃを使うことで、“退屈による夜中の暴走”を防止できます。
やってはいけないNG行動
大声で叱る・追いかける
怖がらせると、猫は“危険な環境”と判断し、余計に興奮してしまいます。
完全に運動量を制限する
本能を抑圧するとストレスが増し、問題行動や体調不良の原因になります。
真っ暗な部屋に閉じ込める
猫のストレスが増大し、トラブルの元になります。
体験談|にゃタゾノの“深夜テンション”が落ち着いた理由
筆者の保護猫「にゃタゾノ」も、以前は夜中に走り回り、棚の上から大ジャンプ…という日々でした。
しかし、夕方の狩り遊び+高所の増設を行ったところ、驚くほど夜の騒ぎが減りました。
本能を満たすことが、猫を落ち着かせる一番の近道だと実感しています。
まとめ|夜の活発さは“問題”ではなく“本能”
猫が夜に元気になるのは、
- 薄明薄暮性の生態
- 狩猟本能
- 生活環境の影響
これらが重なった自然な行動です。
本能に寄り添うことが、猫も飼い主もストレスなく暮らせる秘訣です。
参考文献・注意事項
- 猫の行動学(Feline Behavior)関連文献
- 専門家監修の猫の生態資料
※行動に異常が感じられる場合は獣医師に相談してください。
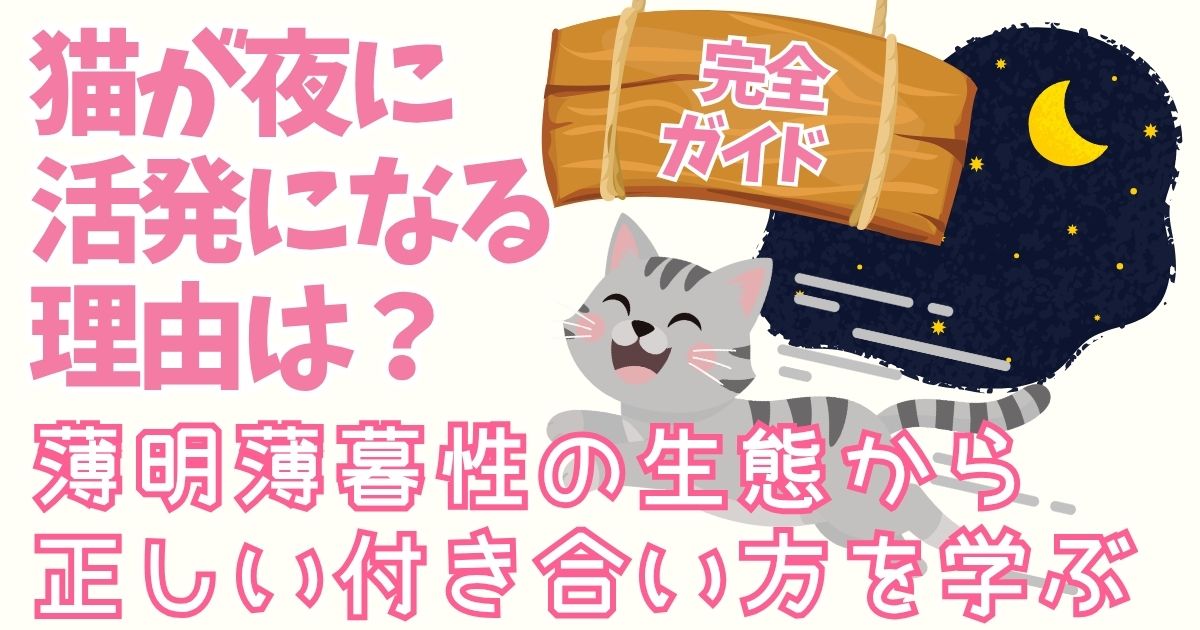


コメント