“なぜそんなに出るの?”初心者がまず知りたい目やに・耳トラブルの基礎
保護猫を迎えたばかりの初心者が驚くのは、「思った以上に目やにが多い」「耳の汚れが黒い」といったトラブルです。
実はこれらは、外暮らし・栄養不足・ストレス・免疫低下といった背景が重なりやすい保護猫にとってとても起きやすいサインです。
獣医師によれば、保護直後の猫は目やに・耳垢・涙やけ・耳ダニ感染が同時にみられるケースも多く、
「迎えて数週間は“観察しながらのケア”が特に重要」だと強調されています。
● 保護猫が目やにを出しやすい理由
保護猫の目やにの原因は多岐にわたります。
- 外生活のホコリ・花粉・風による刺激
- 免疫力低下 → 軽い結膜炎を起こしやすい
- ストレスによる涙腺トラブル
- 猫風邪(ヘルペス・カリシ)の後遺症
特に黄色・緑色の目やには細菌感染の可能性が高く、専門家は「自己処理を続けず、必ず受診を」と助言しています。
● 耳が汚れやすい猫の特徴
耳掃除が必要かどうかは体質や毛質でも変わります。
白猫・長毛種・皮脂量が多いタイプは耳垢が溜まりやすい傾向にあります。
さらに、保護猫は外暮らしである確率が高いため、
- 耳ダニ
- ノミ・ダニの二次感染
- 外耳炎
が隠れているケースも。
獣医師は「特に初診では耳ダニ検査をしておくべき」と推奨しています。
● 初心者が見落としやすい危険サイン
- 片目だけ目やにが多い
- 頻繁に頭を振る・こすりつける
- 耳が赤い/強いニオイがある
- 触ると嫌がる(痛みの可能性)
いずれも「ただの汚れ」ではなく、感染症やアレルギーの兆候。早めにアクションを取ることが大切です。
目やにケアの“正しいやり方”と初心者がやりがちなNG
●使用すべきもの・避けるべきもの
獣医師監修のケアでは以下が基本です。
使用OK
- ぬるま湯
- 猫用アイケアローション
- 清潔なコットン or ガーゼ
使用NG
- 人間用ウェットティッシュ(刺激強すぎ)
- アルコール入り製品
- ティッシュ(繊維が残る)
●正しいふき取りの流れ(図解風の“3ステップ”)
STEP1:手を洗い、猫を落ち着かせる
STEP2:コットンを湿らせ、目頭→目尻へ一方向にやさしく拭く
STEP3:両目でコットンを変える。赤みが出たら中止
専門家いわく、「力を入れすぎないこと」が最も大切だそうです。
●ケア頻度の目安
基本は1日1回。
特に多いのは「寝起き」「ごはん後」。
季節変動(花粉・乾燥)で増える場合は朝晩チェックを推奨されています。
耳掃除の正しいプロセスと“危険を避けるコツ”
● 必要な道具
- 猫用イヤークリーナー(低刺激タイプ)
- コットン or 指サック型イヤークロス
- ご褒美のおやつ
綿棒は使わないのが鉄則で、獣医師会でも強く警告されています。
● 耳掃除の正しい流れ
STEP1:コットンにイヤークリーナーを少量つける
STEP2:耳の外側 → 内側へ“見える範囲だけ”拭く
STEP3:頑固な汚れは数日に分けて取り除く
STEP4:終わったらおやつで“成功体験”に変える
● 耳掃除の頻度と異常の見極め方
基本の目安は月1〜2回。
ただし以下の症状があれば即受診です。
- 黒い耳垢が多い
- 悪臭がある
- 耳をかゆがり続ける
- 赤み・腫れがある

身体が小さく耳と目はひときわ大きく見えます。
“毎日のひと工夫”で健康を守る!トラブル予防と観察ポイント
● お手入れ嫌いにさせないコツ
獣医師は「短い時間 × 高頻度」を推奨します。
数秒でも触れるだけで、触られることへの抵抗が減ります。
- 触ったらすぐ褒める
- 1日数回、顔まわりに軽く触れる習慣を作る
- 嫌がる日は無理をしない
● 季節ごとの重要ポイント
季節ごとにケアすべき内容が変わるため、以下を参考にしましょう。
- 春:花粉で涙・目やに増加
- 梅雨〜夏:湿気で耳トラブル・耳ダニ増加
- 秋冬:乾燥で目の乾燥が悪化
● “健康チェック表”で異常を早期発見
| 部位 | チェック項目 | 頻度 | 異常サイン | 対処法 |
|---|---|---|---|---|
| 目 | 目やに・涙・赤み | 毎日 | 黄色/緑色・腫れ | 拭いて改善なければ受診 |
| 耳 | 耳垢・ニオイ・赤み | 週1確認 | 黒い汚れ・強いニオイ | 自己処理せず受診 |
| 被毛 | 毛並み・乾燥・フケ | 毎日ブラシ | ハゲ・ベタつき | 皮膚病の可能性あり受診 |
体験談:“触れられなかったにゃタゾノ”がケア好きになるまで
我が家の保護猫「にゃタゾノ」は、保護初期は耳ダニがいたため、耳は汚れてとてもかゆそうでした。
早速獣医師を受診し、きれいにしてもらいましたが、手足を拭こうにも顔や耳を拭こうにも、すぐに察知し逃げ隠れてしまいます。
でも、ほどよくあたたかいと心地よいようで、にゃタゾノが目を細めて安心して嫌だけれど拭くのにおうじてくれます。
動物病院で耳ダニチェックと掃除の方法を教わり、1ヶ月後には見違えるほど清潔になりました。
まとめ|お手入れは“健康診断+信頼づくり”の時間
目や耳のケアは、見た目を整えるだけでなく、
猫の健康と心の安全を守る大切なコミュニケーションです。
毎日の観察とやさしいタッチが、保護猫にとっての“安心の証”。
無理せず、焦らず、少しずつ信頼を育てていきましょう。
参考文献・専門家監修情報
- 日本獣医師会:目・耳のケアガイドライン
- 米国動物病院協会(AAHA)猫のヘルスケア指針
- 獣医師インタビュー(行動学・眼科・皮膚科)
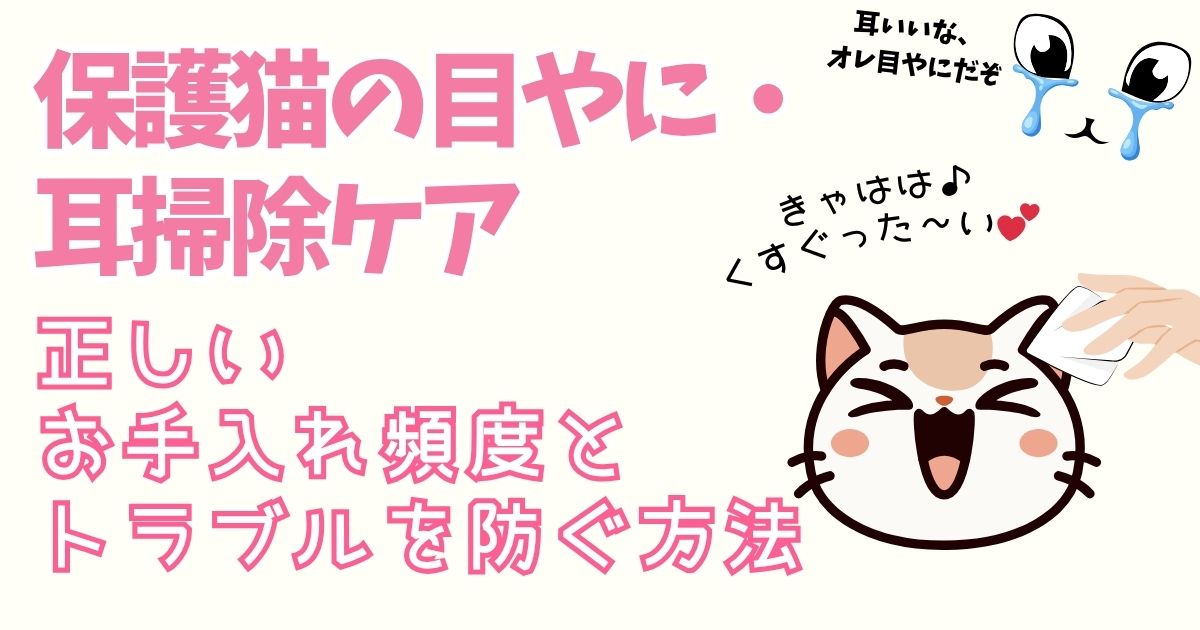

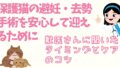
コメント